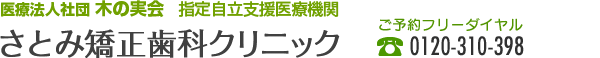ニュース
桑原未代子先生・坂下玲子先生講演会参加報告
日時:2009年2月15日
場所:タカラベルモント東京本社
主催:赤ちゃんから学ぶ会
●はじめに
桑原未代子先生は、医科歯科大学、愛知学院大学、藤田保健衛生大学等でご活躍なさった小児歯科と矯正の分野にまたがる分野のオーソリティーであり、現在、ライオンの歯科衛生研究所に所属しておられる。
先生は、非常に長い間小児と矯正に関わる研究をされ、長年の経験に裏打ちされた小児の成育医療についての語り部ともいえる方である。そんなことから、今回の講演は、今の若い奥さん方やドクターに対して伝授されるような形でのお話だった。
実は、「赤ちゃんから学ぶ会」では、石田房枝先生が中心になって、年に何回か、桑原先生をお呼びして会を開いている。今年も2月12日に茨城県つくば市谷田部の庄司産婦人科小児科医院で、赤ちゃんの患者さんを桑原未代子先生に検診していただきながら、患者さんや見学しているドクターに対してお話くださる会というものを開催している。
そのような背景があって、桑原未代子先生のお話を、もっとまとめて聞く機会を持ちたいということから、今回の講演会が企画された。
●「赤ちゃんから学ぶ会」発足の経緯
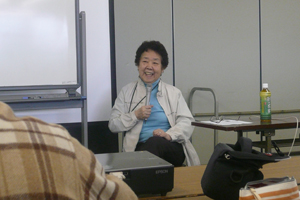 「赤ちゃんから学ぶ会」というのは、赤ちゃんの様々な発育状況や症状を見ることによって、われわれ自身の治療のノウハウや能力を高めていこうとするものであり、赤ちゃんをもっと詳しく観察しようという会である。
「赤ちゃんから学ぶ会」というのは、赤ちゃんの様々な発育状況や症状を見ることによって、われわれ自身の治療のノウハウや能力を高めていこうとするものであり、赤ちゃんをもっと詳しく観察しようという会である。
小児歯科の先生たちにしても、われわれのような矯正のドクターについても、新生児や未熟児と接する機会はなかなかない。クリニックに来る時には、歯はある程度生えている状態であり、歯が生えてこない段階では、われわれのところに来る必要がない。しかし、最近、小児歯科や矯正医にとって、歯が生えてくる前の段階を知ることが大切であることがわかってきた。ポイントとなるのは、母胎の中にいる胎児の段階、または生まれてきてからの授乳や離乳という問題、いわゆる咀嚼・嚥下のシステム構築の中で、つまり初期の段階に問題があるのではないかという考えが出てきたのだ。そのために、赤ちゃんの発育にポイントを定めて見てゆこうという機運が生じた。
赤ちゃんについては、これまでは、産婦人科や小児科の先生たちが関わってきており、歯についてはあまり注目されなかった。われわれ歯科医院にとっても今まで接していない部分であり、あまり注目していないところだった。しかし、実は、そこの部分が非常に重要だということがわかってきて、一昨年、石田先生が中心となって、「赤ちゃんから学ぶ会」がつくられたのだ。
●人は、いつから口呼吸を覚えるのか
会の前半では、桑原未代子先生のお話をうかがった。演題は「口腔機能向上を目指して」ということで、口腔の活動の開始時期と状況についてお話いただいた。先生は、これまでの長い診療歴、研究歴を通して、これまでどのような活動を行ない、赤ちゃんの口の中のことについて、どのような見識を持たれてきたかを話してくださった。そして、これまでの新生児から乳幼児、そして幼児に対する口腔衛生指導及び研究についての歴史を、あますところなくお話しくださり、伝授してくださった。
また、今後の問題についてということで、咀嚼に関する問題について、様々な見地からご教授くださり、新しい課題についても提案をしてくださった。特に、口呼吸について、いつ頃から発生してくるのか。人間の成長発育の中で、生まれたときにはみんな鼻呼吸をするが、いつの頃からか口呼吸を覚えてしまい、常時口呼吸で過ごしてしまう人がいる。それが、何を機縁として、いつの時期から口呼吸が出てくるのか、「赤ちゃんから学ぶ会」に探求していって欲しいという話も出された。
桑原未代子先生には、今後もいろんなお話をうかがいたいと思っている。私自身も桑原未代子先生をお呼びして、お話を聞く会を是非持ちたいと思っているが、先生はご高齢で少し足が弱られているために、時々車椅子に座っておられる状況なので、どうなるだろうか。是非、みなさんにも桑原未代子先生のお話を聞いていただきたいと願っている。
●口腔ヘルスプロモ-ションにおける疫学的研究
会の後半は、坂下玲子先生のお話だった。先生は、兵庫県立大学看護学部教授で、東京大学の大学院のご出身とうかがった。そこで井上直彦先生や伊藤学而先生と一緒に研究をなさってこられた。
どういう内容の研究かというと、口腔ヘルスプロモ-ションと看護ケアの質評価と改善システムの開発ということのようだ。口腔の成長発育とかヘルスプロモーションを考える上で、まず必要となるのは、疫学的研究ではないかと思う。つまり、疫学的な、広い範囲でのデータの蓄積と正確な数値を得ることが非常に重要なことだが、先生はその研究の第一人者である。
私が注目しているのは、先生の研究の中で、沖縄県の宮古島における無歯科医地区における研究活動や埼玉県での口腔公衆衛生活動というものがあるが、その報告が非常に素晴らしい。後に資料として先生の書かれた本を挙げておくので、是非、読んでいただきたいと思う。殊に、坂下先生が東大の井上直彦先生と一緒に書かれた『子どもと口の未来のために』メディサイエンス社刊は非常に良い本だと聞いている。是非、一読をお勧めする。
●研究における車の両輪としての実験学的調査
 坂下先生の講義は、広い範囲の話だった。演題は「咀嚼器官の発達低下について」というお話で、人類の歴史を辿りながら、現在、どのような咀嚼の低下が起こってきているのかについてお話をしてくださった。その上で、対応策などについても様々にお話をしていただいたが、やはりその中で、先ほども述べたように、疫学的調査(ケースコントロールスタディ)が十分なされることが必要だということだった。
坂下先生の講義は、広い範囲の話だった。演題は「咀嚼器官の発達低下について」というお話で、人類の歴史を辿りながら、現在、どのような咀嚼の低下が起こってきているのかについてお話をしてくださった。その上で、対応策などについても様々にお話をしていただいたが、やはりその中で、先ほども述べたように、疫学的調査(ケースコントロールスタディ)が十分なされることが必要だということだった。
更に、もう一つ必要なものとして、ファクターコントロールスタディがあるとも言っておられた。これは、実験学的調査ということだと思う。つまり、マウスやラットなどを使った実験などが疫学的調査と共に進められる必要があるということだ。マウスによる哺乳の形態、離乳食の形態や食事の形態についての実験が、日本とか世界の疫学的なデータと関連して実証されるような形の研究が必要だろうと思う。そういうことをしていかないと、発育低下の原因の究明はなされないのではないだろうか。
ただし、そのような疫学的データの蓄積というのものは非常に労力とエネルギーが必要となる。それについて先生は、そこまでできないときには、症例を一つ一つ集めてゆくということも決して無駄ではないと話された。これは、EBMの構築という問題にもなってくる。実際、すべてがすべて疫学データが取れるかというと、なかなかそうはいかないのが現実だ。また、すべて実験が行えるかというと、それもなかなか不可能なことがある。そういう場合には、症例発表の蓄積とか、演繹学的にその症状を説明するというような手法も必要だという話だった。詳しくは、坂下先生のご本を読んでいただきたい。非常に理論的にまとまっているので、是非、一読されることをお勧めする。この報告を終えるにあたって、資料として本の情報を添付しておく。
<資料>
『食べて、遊んで、育って-お口の中から始めるステップアップ育児』海苑社刊
『子どもとマスターする健康な歯の育て方』合同出版刊
『子どもと口の未来のために-赤ちゃんからの歯科保健』メディサイエンス社刊
『イラスト版歯のしくみとケア-子どもとマスターする健康な歯の育て方』合同出版刊
『むし歯の歴史-または歯に残されたヒトの歴史』砂書房刊